診断書無しでも辞められる
普通に会社は辞められる
まず民法第627条第1項において退職の権利はすべての被雇用者にあり、退職の理由は関係がありません。
- 体調不良
- 仕事がつまらない
- 上司がむかつく
- もっと良い職場が見つかった
体調不良に関わらず上記いかなる理由であっても、退職できるということを知っておいてください。
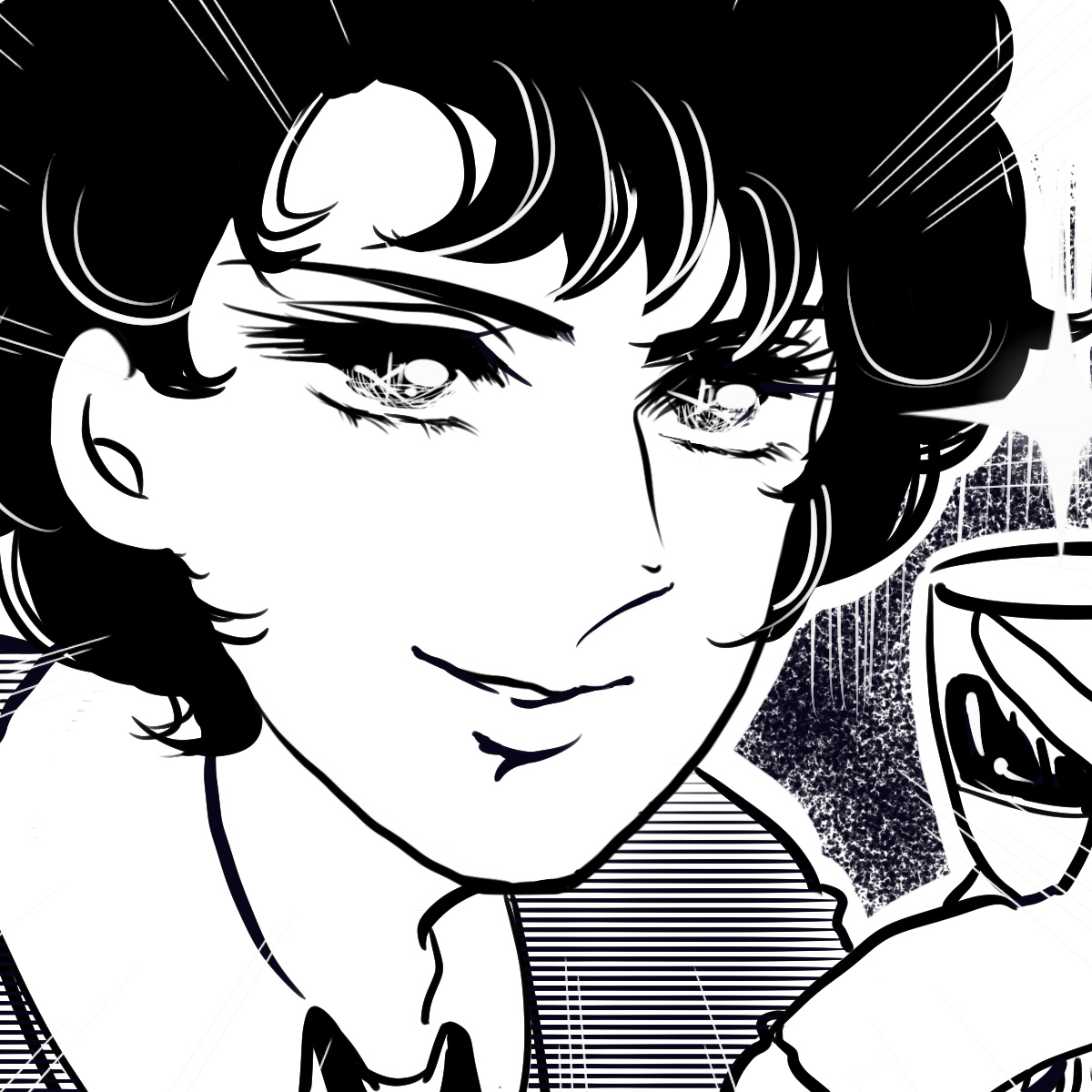
法的には退職に当たって理由は不要です。伝えた方が穏便ですが。
辞めるのに診断書は不要
法的には退職に理由は不要なので、体調不良を理由にする場合でも診断書も不要です。会社から診断書の提出を求められるケースもありますが「プライベートであるため」と拒否は可能で「診断書はないがこれ以上の悪化を防ぐため」と言う理由で退職可能です。
一方で休職して傷病手当金をもらう場合などは診断書が必要になるケースが多いです。
いつ辞めるかを決めるだけ
民法第627条第1項には「退職の意志表示をしてから2週間が経過すれば雇用関係は終了します」とあります。
これは法的な取り決めであって、会社との合意があれば即日でも辞められます。また病気やけがなどやむを得ない理由がある場合は、法的にも即日での契約解除が行えます。
このような法的な取り決めはありますが、基本的には退職日は会社と相談して決めることが一般的です。
嘘はつかない
ちなみに退職の理由は単なる転職だが、円満退職のために「ウソの体調不良を持ち出す」というのはあまりお勧めしません。
- シンプルに心配される
- 同業界の場合転職先の社員と前職の社員が知り合いと言うケースはかなり多い
- 他業界ですら前職の社員とつながりがある人が転職先にいるケースは案外多い
「辞めた後にウソがばれても、その会社にいないから問題ない」というのは一理ありますが、転職先の会社にそれが伝わって「この人はウソをついたことがある人」という評判が広まると、やりづらくなります。
なので円満退職のために「ウソの体調不良を持ち出す」のは辞めておきましょう。
一度病院に行っておく

体調が最優先
体調不良を感じているならちゃんと病院に行っておきましょう。診断を受けて特に問題がないと言われるなら、それはそれで良いことです。それでも会社を辞めたいと思っているなら、辞めればいいだけ。病名に関わらずご自身の意志は常に尊重されるべきです。
それよりも大切なのは自分の身体がどのような状態なのかを正しく知っておくこと。自分ではまだ大丈夫と思っていても、実は治療が必要だったというケースも多いです。
診断書のもらい方
- 診断書を書いてほしい旨伝える
- 診断書の提出先と目的(退職/休職/傷病手当)を伝える
- 病気やケガが診断されれば発行される
初診で病名を特定できないケースもあれば、病名判明したものの発行まで2週間を要するケースもあるので、診断書が必要な場合は速めに病院に行きましょう。
診断書が必要なのは社会保障や、保険等お金を請求するときが主で、退職時には必須ではありません。
特に病名が付かなかったら?
病院で見てもらった結果、病名が付かず疲れているだけというケースもあるでしょう。それが分かっただけでも安心です。
大切なのは体の状態を知ることと、ご自身が「会社を辞めたい」などの意志です。病名がないと会社を辞められないわけでないですし、現に世の中の退職者の多くは体調を理由に退職していません。
むしろ「元気なうちに会社を辞める」ことができるなら、それに越したことはありません。
スムーズな辞め方

辞めるだけなら理由はなんでもいい
何度も言いますが、法的には退職に理由は不要です。ただ大抵の場合は理由を聞かれますし、できれば円満に退職したほうがお互いにとって良いので、回答内容を準備しておいたほうがいいでしょう。
ただ注意点は引き留めに合う可能性もあるということです。わかりやすい例で言えば「体調回復したら復職できるので、休職にしませんか?」など。
一応この辺りの質疑応答も含め、ある程度内容を固めておいた方が良いでしょう。例えば休職を勧められた場合は「今の仕事内容が自分に合っておらず、復職後も同じように体調を崩してしまうかもしれません。一度辞めて自分と自分の体調に合った仕事をゆっくり探したいと思っています」など。
会社のせいとは言わない方が良い
ご自身の体調不良は仕事が多過ぎたり、適材適所でなかったり、上司の存在であったりと、会社側に原因があるかもしれません。ただ会社が原因であると伝えるとややこしくなるのでやめた方が無難です。
ですが退職時にそれを伝えると「なるほど。では○○を改善できるよう努力するので、あと○○か月様子を見てください」みたいな形で、引き留めに合う確率が上がります。
なので会社が原因ではなく、自分の体調なり状況なり、仕事との相性なりを退職理由にした方がスムーズにことが進みます。
限界なら退職代行
今日限りで辞めないと、自分の心身が持たない!と言う場合は退職代行が最終手段です。円満退社とはいきませんが、それよりも健康の方が大切です。退職代行とは
- 自分に代わって退職したい旨伝えてくれる
- 基本会社の人と関わらずに辞められる
- 3~5万円の依頼料
ただ一度冷静になって退職代行を利用する前に、数日お休みをもらいましょう。そこで改めてゆっくりと考えて、やっぱり続けられないとなれば上司に連絡し退職したい旨伝えます。
同業界での再就職が難しくなるなどのリスクもあるので、退職代行はあくまで最終手段としましょう。
休職の選択肢

辞めたいか否かを冷静に判断
会社や仕事が体調不良の原因だとして、会社を辞めたいか続けたいのかを改めて考えてみましょう。休職して傷病手当金をもらいながら生活し、復職後は別の部署にしてもらうというケースも多くあります。
特に仕事内容が自分に合っていないとか、繁忙期で忙しすぎるのが体調不良の原因だったりする場合は、部署異動や復帰時期を考えれば続けられるかもしれません。
今の会社に残っていたいという意思があれば検討するべきで、辞めたいと思っているなら休職の選択肢は消してしまって問題ありません。
休職なら傷病手当金が出る可能性アリ
休職であれば傷病手当金をもらえる可能性があります。金額は月額約25万を上限とし、おおよそ月給の2/3です。
https://www.tfkenpo.or.jp/member/benefit/rest_a.html
- 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
- 続けて3日以上休んでいる
- 給料等をもらえない(給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。)
一方で傷病手当金は健康保険の制度なので、退職してしまうと受けられなくなってしまいます。ただ退職後は失業保険の枠組みの中から失業保険を受けることができます。
休職の場合は診断書が必要
退職の自由は本人に認められていますが、休職に関しては会社の判断なので希望したからと言って必ずしも通るわけではありません。
なので基本的には診断書が必要となるので、人によっては退職よりもハードルが高いと感じるかもしれません。
また会社によっては休職の制度がない場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
辞めた後の生活

失業保険金/傷病手当の受給
過去2年間の間に12か月以上失業保険に加入していれば、自主都合退職であっても失業保険を受けることができます。
ただ失業保険は「今すぐ働ける状態で働く意欲があるが、職場が決まっていない状態の人」に対して生活を保障する制度で「傷病中で働けないが、働く意欲がある人」に対しては傷病手当と言う制度があります。
金額はどちらも同じで、ややこしいのが「傷病手当金→健康保険」「傷病手当→失業保険」と似た名前の制度があることです。
退職後に関しては基本的に失業保険(ハローワーク等)の枠組みの中で支援を受けられるので、調べてみましょう。
療養し回復に努める
焦って転職活動をしてしまえばまた心身に負担をかけることになりますし、しっかりと職場環境や仕事内容を吟味しないと転職後にまた身体のに負担をかけかねません。
なので退職後はしっかりと療養しましょう。とはいえずっと家で寝ていれば全て回復するものでもありません。
特にストレスなどの疲労から回復するには、日に当たったり、体を動かしたり、人と喋ったりと活動することで回復することもあるので、自分が心地よいと思えることがあれば積極的に取り組んでいくことをお勧めします。
自分を振り返ってみる
療養し少しずつ活力を取り戻せてきたなと感じたら、改めて自分のことを振り返ってみましょう。
- 体調を崩した原因は何か
- これまでに楽しいと思えたことはなにか
- 自分の好き/得意は何か。嫌い/苦手は何か。
- 何のためなら自分は頑張れるか
振り返ったことは脳内で完結させず、必ずノートの書き出しましょう。書き出すことで思考が整理され、今後自分がどうすればよいのかに思考を進ませることができます。
余裕ができたら次のステージへ

目標を立ててみる
療養して回復し、自分を振り返って思考を整理したら、目標を設定してみましょう。自分がやりたい、達成したいと思える目標ならまずはなんでもいいです。
- 推しをメジャーデビューさせる
- マイホームを買う
- 結婚する
- Youtuberになる
また目標は複数個あるのが一般的です。推しがメジャーデビューするまで追いたいし、マイホームも買いたいし、結婚もしたいというケースです。
全て同時に全力でとはいきませんが、時期に応じて力配分を変えながら追っていけば問題ありません。「自分には目標がある」ということが重要です。
目標に沿った仕事を探す
目標が見つかったら、その目標達成のためにどんな仕事をするかを決定します。Youtuberになりたいからと言って、必ずしもYoutuberの事務所や映像制作の会社に入る必要はありません。
平日仕事が終わって、Youtubeの作業をする時間を取れる仕事、その元気を残せる仕事であれば十分です。その代わり給料はあまり高くないかもしれません。何を取って、何を取らないかが「選択をする」ということです。
振り返りを活かす
また振り返りで「なぜ体調を崩したか」「嫌い/苦手はなにか」が分かったはずなので、これらの要素からはなるべく距離を置ける仕事が良いでしょう。
一方で「好き/得意」に合致するとより良いですが、好きを仕事にするのは難しく多くの人が実現できていません。それよりもNGを避けることの方が重要です。
では「好き/得意」を捨てているかと言えば、先に設定した目標に「好き/得意」が含まれており、人生単位では関われているはず。自分にとってのNG要素が少ない職場で十分です。



