副業OKな会社が増加中
転職サイトで探せる
転職サイトで「副業OK」の会社を探すのが一番手っ取り早いです。最近では副業OKの会社が増えていますし、それを募集要項に明記する会社も多いです。
さらに言うと転職サイトであるにも関わらず「副業として弊社に参画する形でもOK」とする会社も増えて来ています。
この場合は業務委託という形になるかと思いますが、いざ探してみると結構副業OKとしてる会社は多いです。
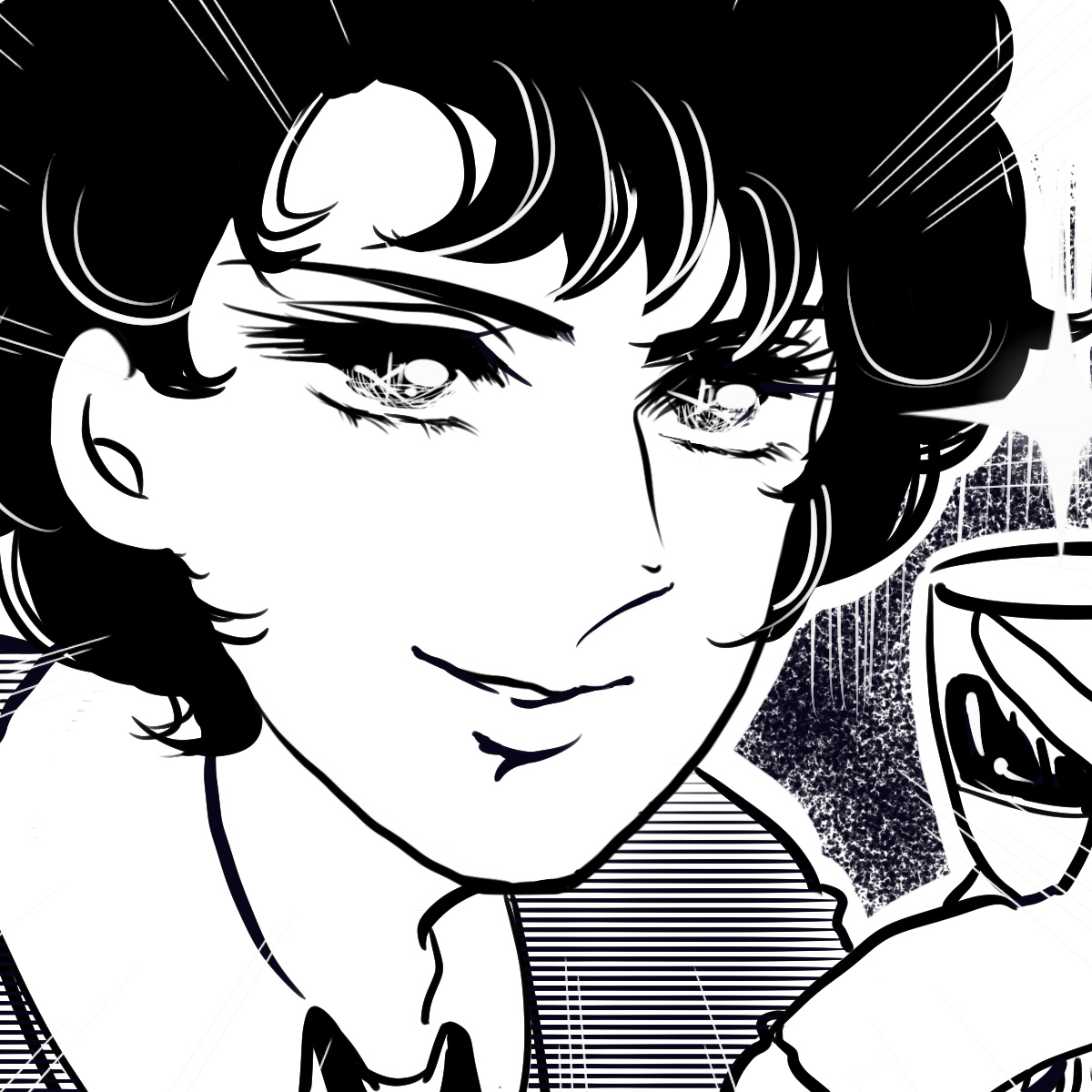
転職サイトの検索フリーワードに「副業」「副業OK」などと入れて検索しましょう!
IT業界
業界で言えばIT業界では副業OKの会社が、他の業界に比べ多いです。理由は以下。
- 「会社に尽くせ」という古い価値観の経営者が少ない
- 副業したほうがスキルアップにつながり、本業に活きる
- リモートが進み最早副業を止められない
- 副業OKでないと人が採用できない
IT業界では当たり前になりつつありますが、この流れはほかの業界にも波及しつつあります。
厚労省が副業ガイドラインを策定
副業OKの流れはIT業界では以前から起こっていましたが、平成2018年に厚労省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表したことにより、一気に加速しました。内容をざっくり挙げると
- 労働時間外に副業するのは個人の自由であるべき
- ダブルワークによって体調を崩さないように留意
- 本業がおろそかになる場合、企業は副業禁止してよい
- 守秘義務や競合への加担には留意
「むやみに禁止せずルールを守って副業しよう」という内容で、どちらかといえば労働者側の権利を守る意味合いが強いです。
厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン
大手でも副業解禁の流れ
厚労省の副業に関するガイドラインを受けて、歴史ある業界・企業でも副業解禁が進んでいます。
- 三菱UFJフィナンシャル
- 富士フイルム
- ソニー
- キリンホールディングス
- 日産自動車
- 花王
あくまで一例ですが、このように大手で副業OKが増えると、それ以下の規模の会社では採用が難しくなるので、大手に倣って副業解禁という流れが進んでいます。
実は副業OKだけではダメ

時間が取れるかの方が重要
副業OKだからといって、現実的に副業ができるかどうかは全く別の話。副業もある程度時給換算できるからです。
ご自身にすでにスキルがあって時給2000円くらいは稼げるとなった場合、月10万欲しければ月50時間副業に従事する必要があります。
準備も含めると毎日休まずやって1日約2時間ほど。仕事の前後にこの時間が実際取れるかが非常に重要となるわけです。
リモートワークが最強
副業の時間が取れるかが重要なので、働き方としてはリモートワークが最強です。2時間かかる往復通勤時間を0にできますし、それにかかる準備の30分も短縮できます。
さらに決められた仕事を効率的にこなせば、業務時間中でもちょこちょこ副業の作業に充てられます。はっきり言って副業を本気でやるならリモートが最強です。
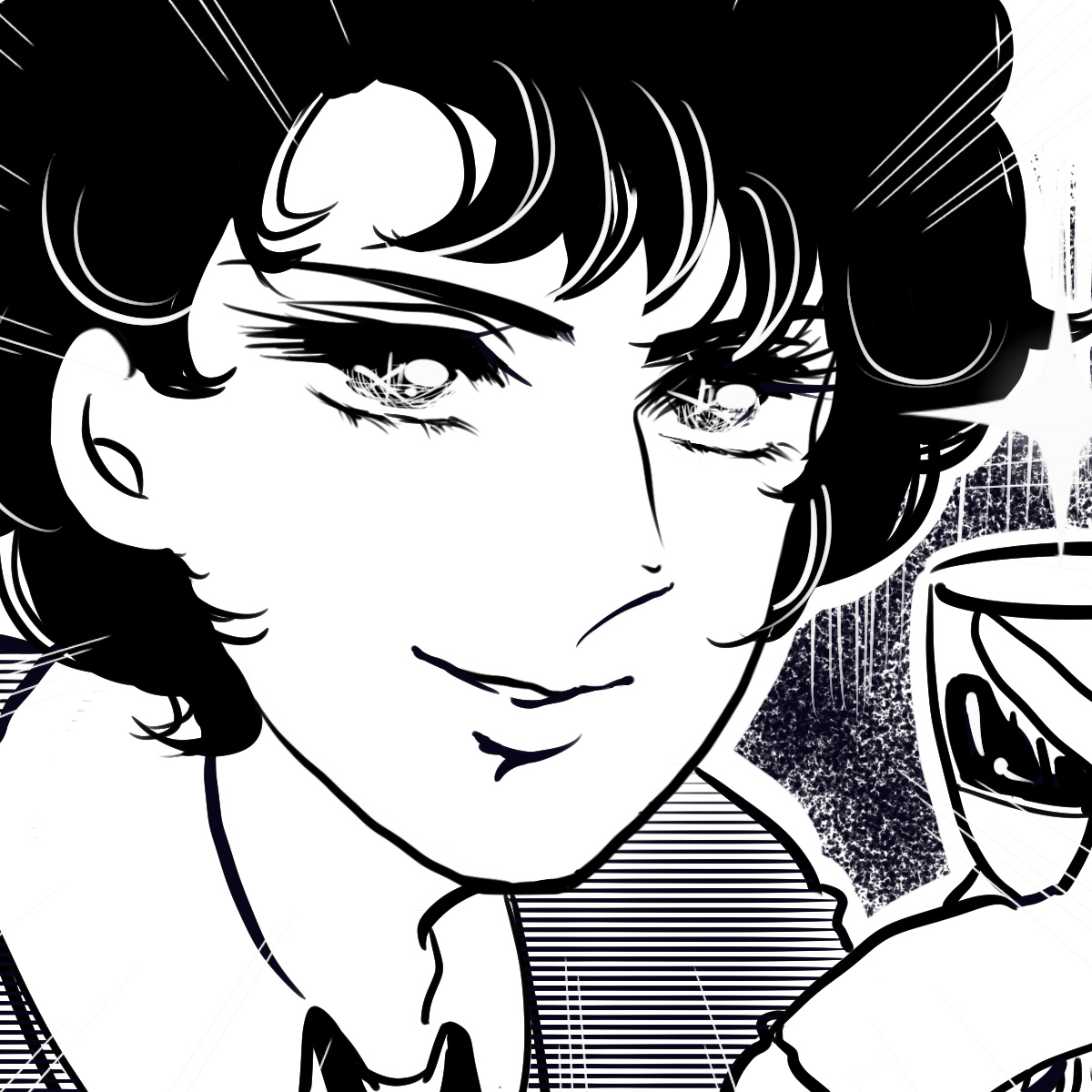
知人に業務時間の8割を副業に充てて、本業以上に稼いでいる猛者もいます
残業やストレスの実体
もちろん残業が多ければその分副業に充てられる時間は限られるほか、仕事のストレスや疲労も考えなければいけません。
仕事に行く前でも、帰ってきてからでもいいんですが、毎日数時間くらいは副業に充てたいです。その体力や精神力が残っているかも当然重要。
ヘトヘトでストレスもMAX。その状態でさらに副業をやるとなれば心身が持たないか、多くの場合副業を放置することになります。「余力を残せる仕事」であることも重要です。
理想は副業とシナジーのある仕事
さらに理想を言えば、副業と本業に相乗効果を持たせたいですね。例えば本業プログラマーの人がプログラミングで副業する例なんかは相乗効果がMAXです。
- 本業:EC/副業:せどり
- 本業:営業/副業:営業代行
- 本業:記事メディア/副業:ライター
自分の本業に合わせて副業を選ぶパターンと、やりたい副業があってそれを加速させるために近い業界/職種に転職するパターンがあります。
「本業で得た知識を副業に」またはその逆もできるので効率的ですが、本業と副業が全くの別物でも副業の時間さえ取れれば問題はないです。
副業NGの会社で副業する方法
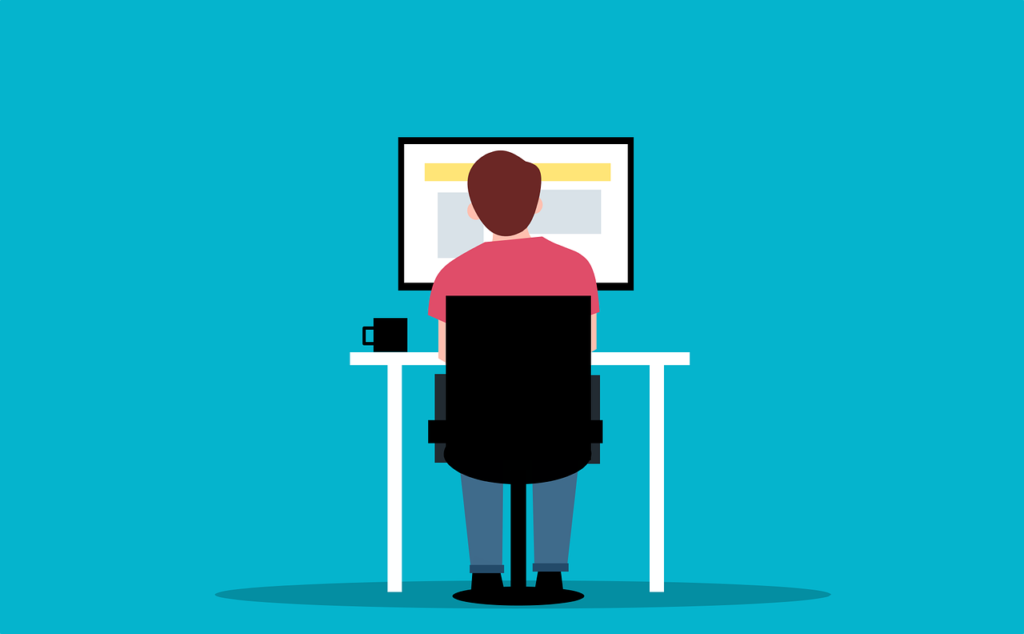
個別にOKをもらえることもある
厚労省の副業に関するガイドラインにおいて、以下の場合は副業の制限ができるとされています。
- 業務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏洩する場合
- 協業により自社の利益が害される場合
- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
つまり上記状況を回避できる副業であれば、個別に認められる可能性があるということ。
もし今の会社が副業OKじゃないなら「本業に絶対に支障をきたさないですし、そのサインも書くので副業を認めていただくことは可能ですか?」と相談してみましょう。
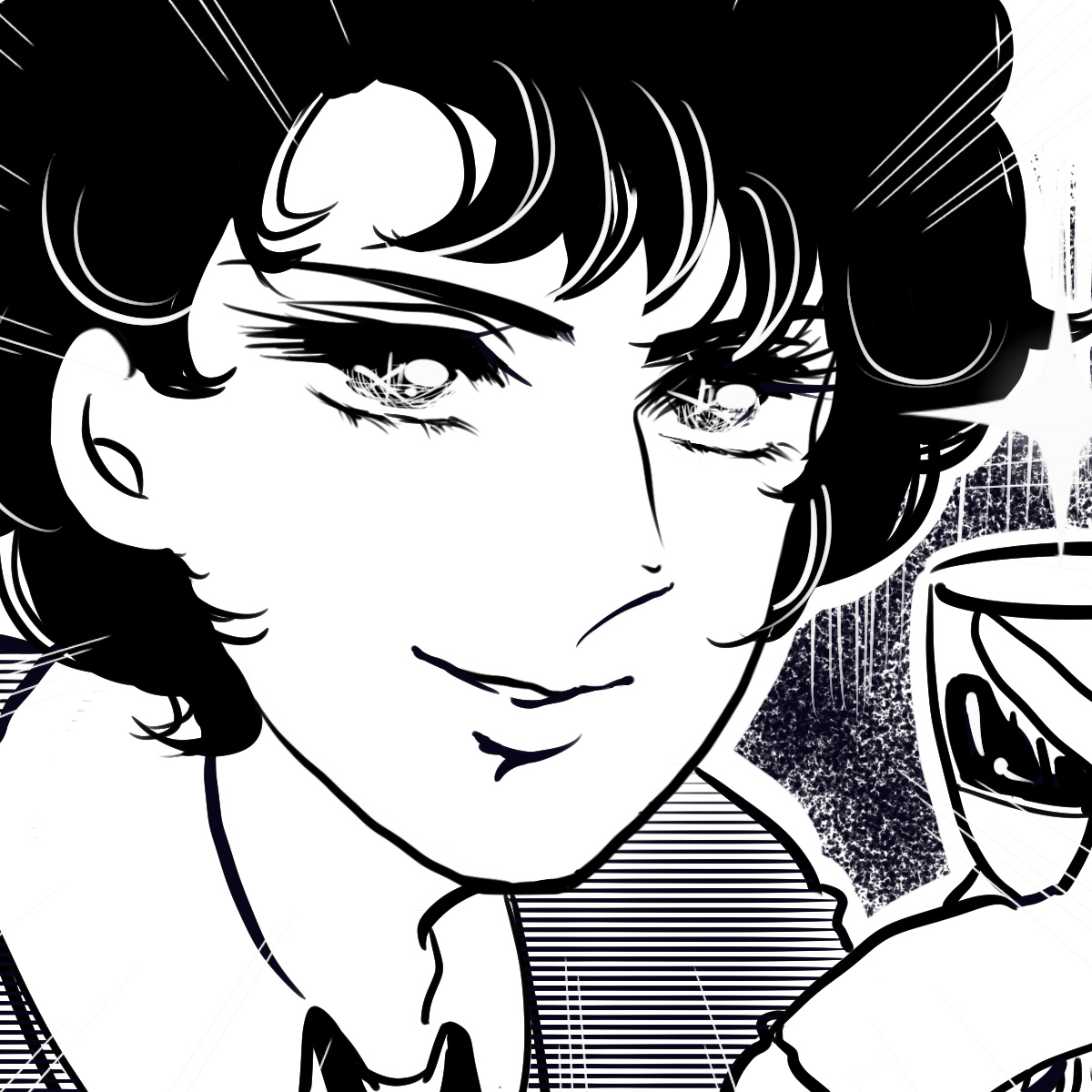
筆者は勤め先に他社の役員をやる許可を個別に取ったことがあります。内容は詳しく聞かれましたが「本業に支障がなさそうだしいいよ」ということでした。
副業がバレるパターン
許可を取らず副業をやって会計上バレる場合は、以下です。
- 年間20万を超えると確定申告が必要になる
- 確定申告すると住民税天引き額が変わる(増える)
- 住民税の天引き額は市区町村から会社に直接連絡が行く
- 給与担当が「なんかこの人の住民税上がった?」と勘づく
さらに付け加えると
- 年間20万超えなくても本来は市区町村に届け出る必要があり天引き額変わってバレる
- ↑ただほとんどの人が申告忘れているので、事実上20万以下はバレない
- 年間20万円を超えて確定申告しないのは、脱税なので普通に違法
会計上はこのような仕組みなので年間20万円以下ならバレないですが、多くの場合は同僚に副業やっていると喋った結果、いつの間にか広まってバレるケースの方が多そうです。
20万超えてもバレない方法を使う
確定申告時に住民税を天引きではなく、自分で直接支払う形式にする形で申告すれば会社に住民税の増額がバレずに済みます。
ですが当然ながら給与担当は「なんでこの人の住民税は突然天引きじゃなくなったんだ?」ということは気づきます。
なので年間20万円を超えそうなら基本的には個別に副業の許可を取るか、副業OKの会社に転職した方が良いでしょう。
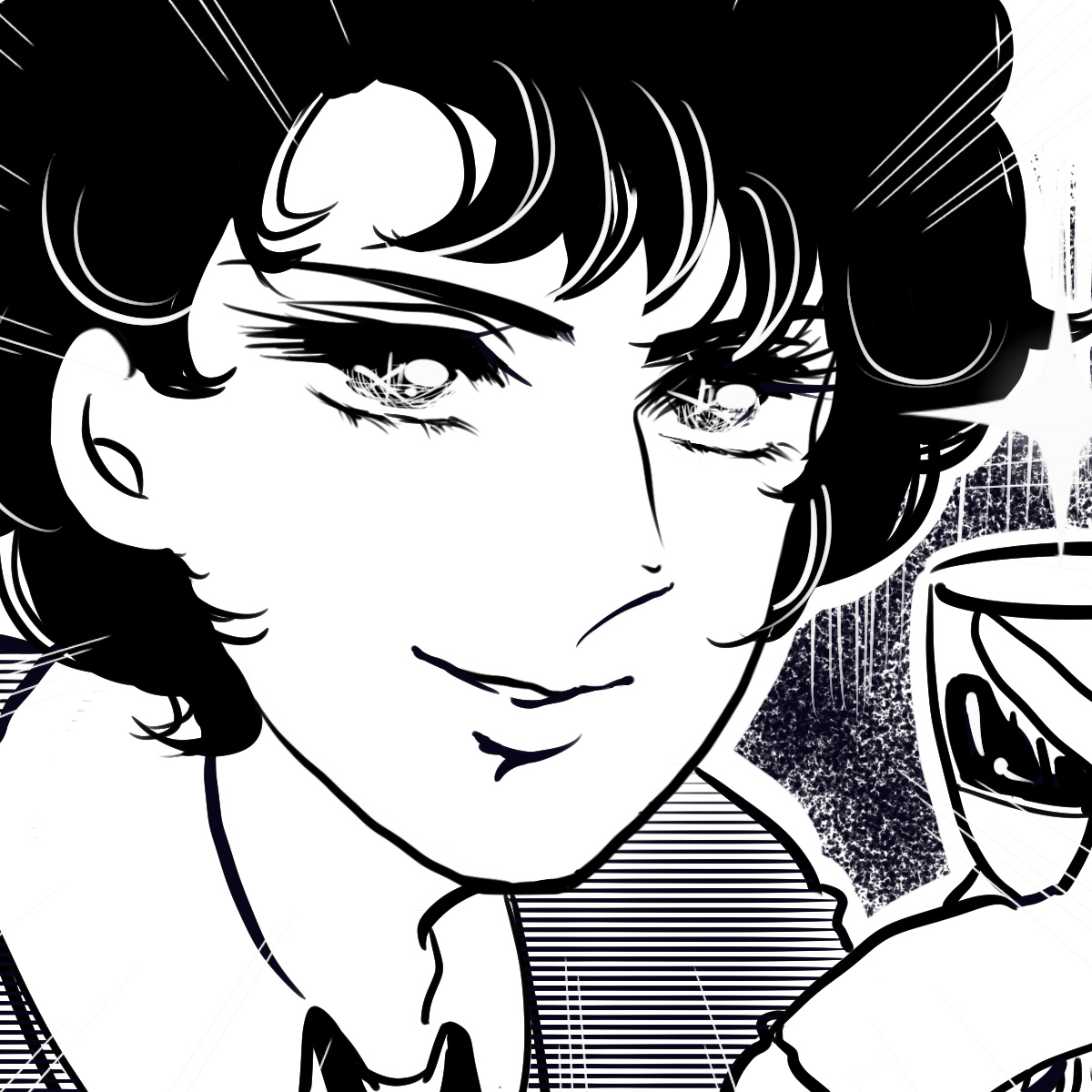
ちなみに年間20万稼ぐのって結構大変です。
独立を見据えるなら雇用形態も考える

正社員やフルタイムにこだわらない
「副業が軌道に乗ったら独立したい」と考えている人は、正社員にこだわって転職活動をする必要はありません。
契約社員・派遣社員・業務委託・アルバイト等で生活できる最低限の給料だけもらい、全力で副業に取り組むという選択肢は十分あり得ます。
またフルタイムではなく時短勤務などで、がっつり副業時間を取るのもありでしょう。本気で取り組めば時給換算で副業が本業を上回れるので、最初から本業の時間は少なめにするという戦略です。
契約や派遣という選択肢
今は正社員でも今後は副業頑張りたいから、契約社員や派遣社員での転職を目指す。というのは有効な選択肢。
事務系やオペレーター系の業務なら週1日出社/週4日リモートワークのような、超副業向けの仕事も結構増えて来ています。
正社員と比べると給料は落ちるので、副業で絶対に稼ぐという覚悟ができている人向け。副業が軌道に乗らず「やっぱ正社員に戻りたい」となっても、すぐに正社員で転職できるかはかなり怪しいです。
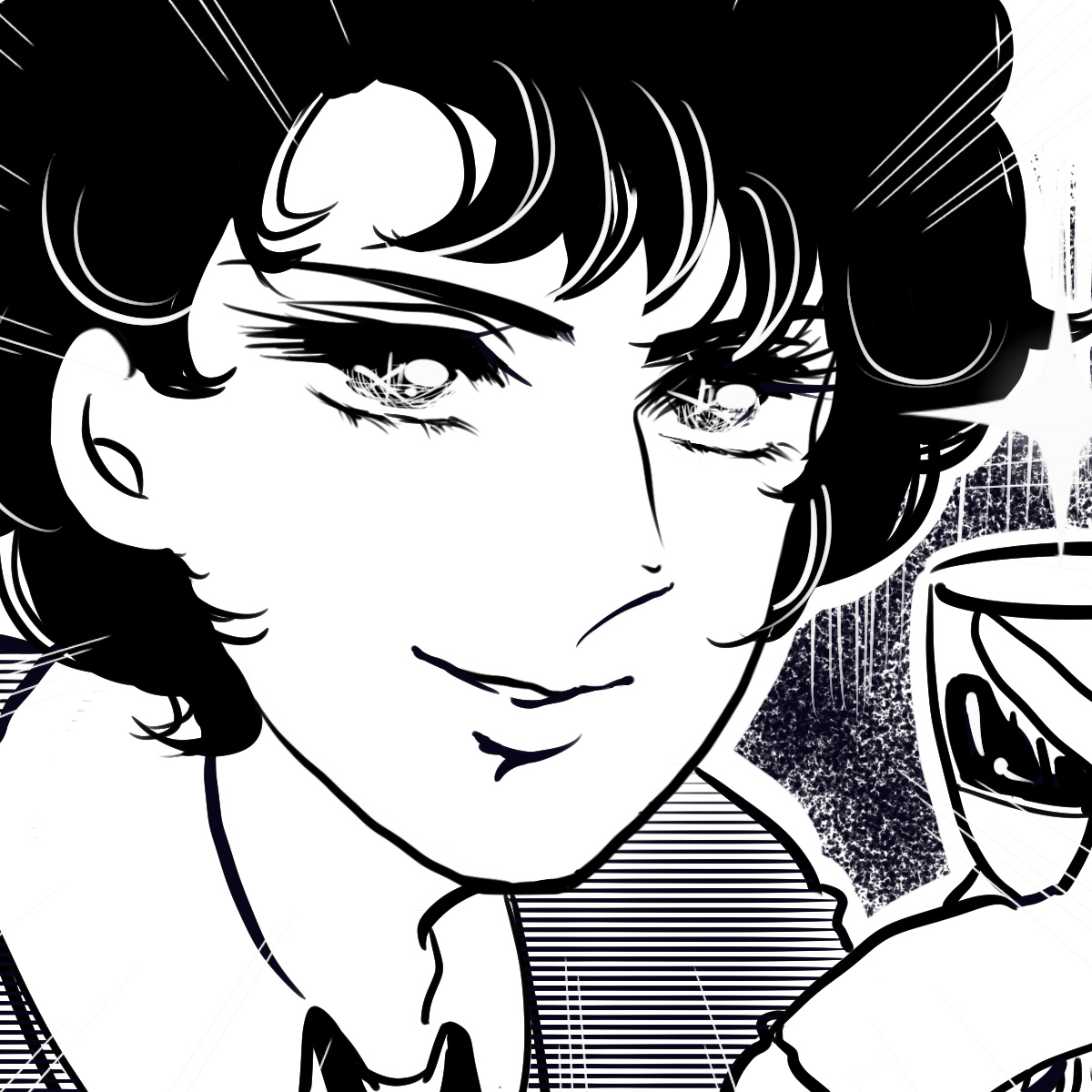
独立するために、時短の契約社員を選んで副業を本気でやり、実際に独立して年収2000万になった知人がいます。
業務委託(非雇用契約)で仕事を受ける
最早何が本業か不明ですが、週3日だけ働くというスタイルです。業務委託なので雇用契約ではなく、どちらかと言うと副業で仕事する場合に結ばれる契約形態です。
つまり誰にも雇用されてないのでフリーランス。社会保険やら納税やらは自分でやらねばなりません。
ただ業務委託の場合は、ある程度専門的な知識やスキルが必要なケースが多いので、誰でもできるわけではありません。
おすすめの立ち回り

副業で何をやるかを決めとく
すでに副業を始めているなら問題ないですが、これから副業する人は転職する前に、副業を始めておきましょう。副業NGでも年間20万円以下なら基本バレないです。
副業のジャンルによっては、本業も副業と相乗効果がある会社の方が良いですし、そもそも「副業やってたけど自分に合わない」となれば転職先の条件が変わります。
なのでまずは副業を始めてみて、何のジャンルで副業するかをある程度決めておいた方が良いです。
副業の時間を作れる働き方を選ぶ
副業で稼げるかどうかは、結局のところ1日何時間副業できるかどうかです。1日1時間の人と1日3時間の人では後者の方が3倍稼げると思いきや、それ以上に稼げます。
なぜならスキルアップも3倍の速さになるので、作業のスピードやクオリティが上がり結果的に時給換算で効率が良くなるためです。
- リモートワーク
- ↑無理なら通勤に時間がかからない
- 残業少ない
- 仕事の後に副業出来る元気を残せる
副業OKなのは当然として、どれだけ自分が副業出来る時間を確保できるかを考えましょう。
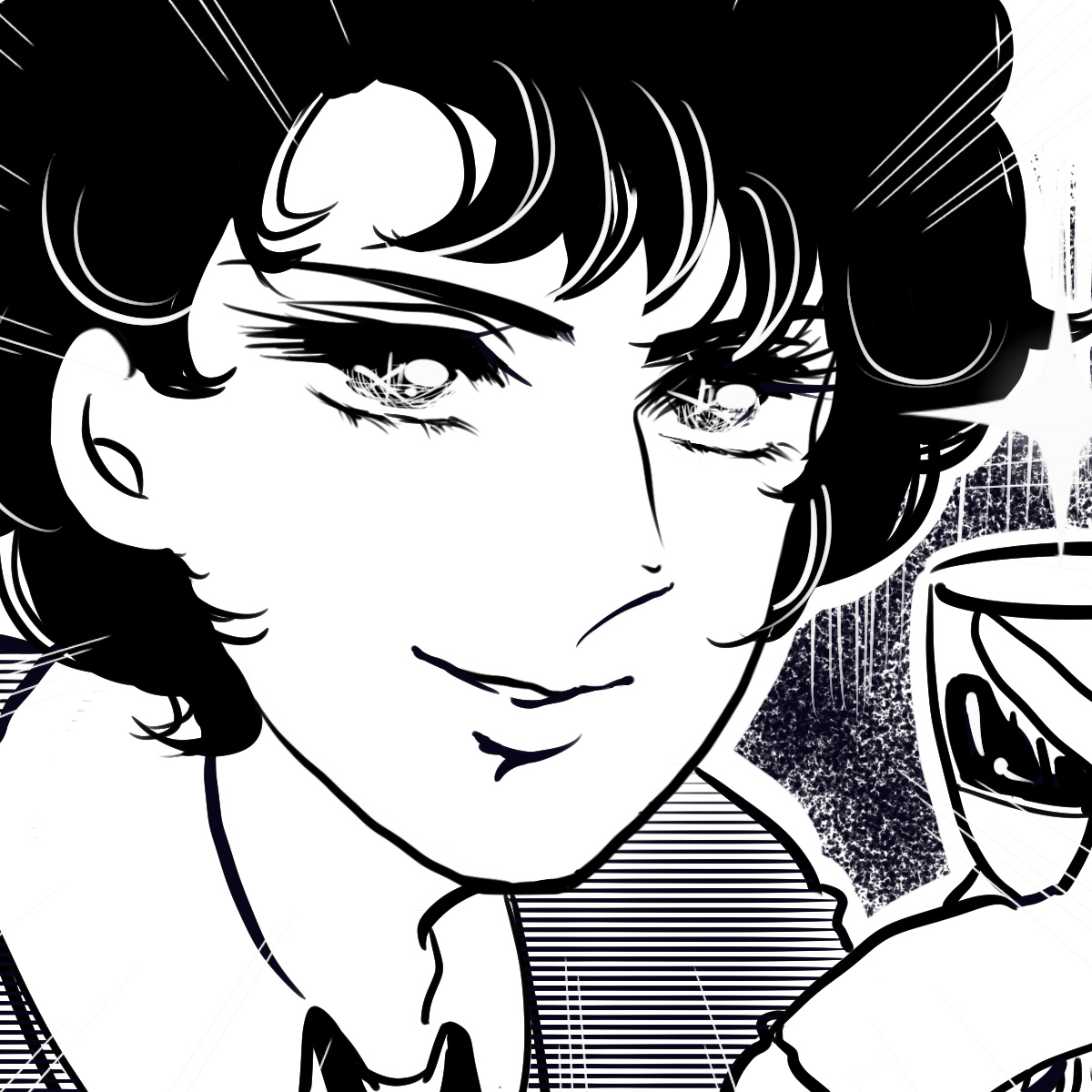
副業成功の絶対条件は「時間を確保」できることです。
副業とシナジーのある会社を選ぶ
必須ではないですが、やはり本業と副業が近い分野だと何かと無駄がありません。なのでやりたい副業が決まっていれば、副業に活かせる本業を選びたいです。
- 本業:EC/副業:せどり
- 本業:営業/副業:営業代行
- 本業:記事メディア/副業:ライター
ただ優先順位としては以下の順。
- 副業の時間を確保できるか
- 相乗効果があるか
副業OKの会社はたくさんあるので、その中でもどれがベストかをしっかりと吟味したいですね。


